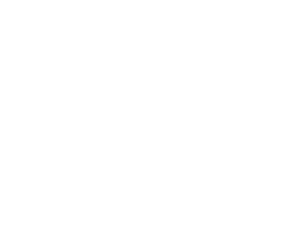1996 McLaren F11996年式 マクラーレン F1
SOLD OUT UPDATE: THURSDAY,APRIL,30,2015 終了・史上最高のスーパーカー
・唯一のボディカラー
・新車、国内未登録車両
“国内に眠っていた新車のマクラーレンF1”
以前販売させていただいた車両のご紹介です。
当個体は、日本国内に未登録のまま保存されていたマクラーレンF1で、恐らく、世界中を探しても見つかることはないであろうと思われた、究極のコンディションを誇る一台でした。
クレイトンブラウンという外装色は、マクラーレン社の株主にして取締役であった人物の名前が付けられたもので、この一台のためだけに用意されたボディカラーでした。
プロトタイプを除く全てのロードバージョンF1の中で25番目に製造された個体で、現在は海外へ輸出されています。
“マクラーレンF1の歴史”
マクラーレンF1は、マクラーレン社の長年に渡るF1トップチームとしての経験をもとに、最先端の技術を採りいれ、一切の妥協を排し、高価な素材(カーボンファイバー、ケブラー、チタニウム、マグネシウム、金)も惜しみなく活用して造られた、20世紀のロードカーの金字塔ともいうべき作品です。
軽量であることを最優先するべく、製造に3000時間もかかると言われたCFRP(炭素繊維強化プラスチック)製モノコックボディを採用しています。
1998年3月31日には時速372kmを達成し、市販車最速記録を打ち出しました。(非公式ながらレブリミットを解除した状態では390.7km/hを達成していました)
チーフエンジニアであるゴードン・マレーが、その開発において常にベンチマークとしていたのはホンダNSXです。自身も7年間に渡ってNSXを所有したという経験を、F1の開発にフィードバックしました。
後年ホンダ社によって行われたインタビューによると、「NSXを運転した瞬間、これまで参考にしてきたフェラーリ、ポルシェ、ランボルギーニといった車のことは頭から消え去った」、と、マレーは告白しています。特に彼がNSXから学んだことは、実用性と快適性の高さと、ハンドリング性能でした。
マレーがエンジン開発のコンセプト段階でこだわったのは、自然吸気であることでした。ターボなど過給器を使えば、確かにパワーを上げることはできますが、信頼性と扱いやすさを損ねると判断したのです。
当初、マレーはホンダに、ロードカー用エンジンの開発を依頼しました。当時、マクラーレンがF1選手権において常勝を誇っていたのは、日本のホンダ製エンジンとのコラボレーションも大きな要因だったからです。
しかし、当時のホンダ研究所は、「ブロック長が600mm以下、重量250kg以下で、550馬力以上を発生」というマレーの求める設計条件に怯んでしまったのか、ロードカー用の大排気量マルチシリンダー自然吸気エンジンを開発することにあまり乗り気ではなかったらしく、結局、マレーはBMW M社へ、そのエンジン開発を依頼することになります。
ポール・ロシュが設計したエンジンは、マレーの出した条件通りのサイズに収まり、圧縮比11:1の6.1リッター自然吸気V12から627馬力を発揮しました。
サスペンション設計においても、ハンドリング性能を重視する一方で、快適性も追求しました。その考え方は、今日のマクラーレン製スーパースポーツにも生かされています。
あくまでも軽量であることを善としたため、電子制御の介入しないブレーキシステムを採用しました。そのため卓越した運転技術がなければ乗りこなすことが難しいと言われています。
こうして車重わずかに1138kgに対し、627馬力という大パワーエンジンを獲得。1トンあたり550馬力、パワーウェイトレシオ1.8という、現代レベルで考えても常識はずれのスペックを持つに至ったのでした。
車体の開発において、最も注意深く考慮されたのは前後重量配分でした。ドライバーズシートを中央に配置する3シーターという風変わりなレイアウトもそのためです。マレーが若いころから3シーターカーを夢見てきたことから採用された、という裏話もありますが、フューエルタンクとエンジンのちょうど前にドライバーを配置することが最も望ましい、という物理的な見地から導かれたアイデアだったのです。
インテリアの装備品も快適であることに気を配っていました。軽量なCFRP製シートはこれまた軽量なコノリーレザーで覆われたハンドメイドで、シート、ステアリング、ペダル位置は固定でしたが、注文時にオーナーに合わせて作られています。
車内全域をカバーするよう、高性能なエアコンを採用。この考え方は、後のスーパーカーにも大きな影響を与え、高性能と快適性の両立が常識となっていきます。
しかしながら、販売は当初の想定よりも振るわず、1992年から98年の間に64台が製造されたに留まりました。5台のプロトタイプと完全なレースカーであるGTR(28台)、公道走行可能なスペシャル仕様のLMやGTを含めても、総生産台数はわずかに106台となっています。
販売終了後もマクラーレン本社によるアフターサービスが充実しているため、新車同様にオーバーホールすることも可能なほか、クラッシュした車両の復元も可能です。
現在においてもスーパーカー設計のお手本とされるモデルで、近年その評価は高まるばかり。海外オークションにおいては、10億円以上のハンマープライスを叩き出すことも珍しくはありません。
-